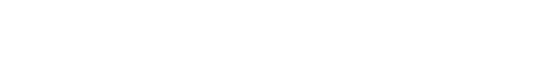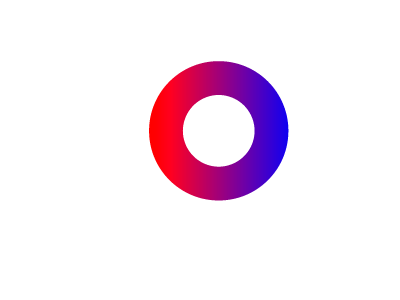三業惑乱
三業惑乱とは、
真宗史上最大の教義安心上の論争です。
江戸時代の1797年から1806年までの約10年間にわたります。
教義論争から権力争い、流血の惨事になり、幕府まで介入し、
最後は本願寺のトップの学者が、地方の僧侶に敗北することになりました。
一体何が問題になったのでしょうか。
また、私たちはそこから何を学べるのでしょうか?
目次
能化とは
三業惑乱について理解するには、まず基礎知識として
能化について知らなければなりません。
江戸時代、浄土真宗本願寺派(西本願寺)では、親鸞聖人の教えが正確に伝えられるように、能化制度が設けられていました。
能化とは、本願寺内で、教義と安心を取り仕切る最高責任者のことです。
安心とは信心のことです。
能化は法主と同格の格式で振る舞い、京都と地元の寺を往復する時は、小さな大名行列のようなものでした。
もし能化に「間違っている」と言われた僧侶は、もう生きてはいけません。
能化はそんな絶大な権力を誇っていたのです。
能化の初代は西吟
2代目は知空
3代目は若霖
4代目は法霖
5代目は義教
6代目は功存
7代目は智洞でした。
三業惑乱の発端
越前(福井県)ではずっと昔から、「十劫安心」という異安心が、勢力をふるっていました。
「十劫安心」は、「無帰命安心」ともいわれます。
「安心」とは「信心」のことで、
「無帰命」とは、阿弥陀仏に救われていない、ということです。
異安心とは異なった安心のことで、親鸞聖人、覚如上人、蓮如上人の信心は同じだから、これらの方々の信心と異なる信心を異安心といいます。
「十劫安心」というのは、「十劫の昔に、すでに我々は助かってしまっているのだから、今さら求めることも、聞き歩くこともいらない」という信心のことです。
浄土真宗の8代目、蓮如上人は、すでにこれが間違いであることをこう教えられています。
「十劫正覚の初より、我等が往生を、弥陀如来の定めましましたまえることを忘れぬが、すなわち信心のすがたなり」といえり。
これ、さらに弥陀に帰命して、他力の信心を獲たる分はなし。
(御文章)
現代でも、救われてもいないのに、
「私たちはすでに救われている」とか、
「救いはすでに届いている」とか、
「救われていることに気づいたのが信心だ」というようなものは、
みな十劫安心の一種です。
この間違いを正すため、2代目の能化、知空の頃から
帰命の一念を強調していました。
そしてついに本願寺は、6代目の能化、功存を越前(福井)へ派遣しました。
功存は、阿弥陀仏をたのむ一念の体験が肝要であることを力説し、
十劫安心を徹底的に破りました。
たのむ一念が肝要であることは、蓮如上人『御一代記聞書』にこう教えられています。
たのむ一念の所肝要なり。(御一代記聞書)
さらに福井県の僧侶や門徒を集めて法話を開き、間違いを正し、
本当の浄土真宗の教えを明らかにしました。
この時の法話が『願生帰命弁』という本になっています。
このように十劫安心を正したのですが、それによって、振り子がふれるように、今度は逆の極端に振れていきます。
三業惑乱の問題
1797年、功存が病気で亡くなると、弟子の智洞が能化を継ぎました。
智洞は能化に就任すると、龍谷大学の前身である本山の教育機関の学林で、『大無量寿経』の講義をしている時、全国から集まった学生に、
「三業で阿弥陀仏をたのまなければ助からない」
と教えたのです。
「三業」とは、身業と口業と意業のことです。
「身業」とは身体でやること、
「口業」とは口で言うこと、
「意業」とは心で思うことです。
三業で阿弥陀仏をたのまなければ助からないというのは、
心で阿弥陀如来にお願いしなければ助からない。
口で「助けたまえ」と言わなければ助からない。
体でお願いしなければ助からない。
心と口と体でお願いしなければ助からない、というものです。
これを「三業安心」とか「三業帰命」ともいいます。
ところが、浄土真宗の教えは「信心正因」です。
親鸞聖人は、こう言われています。
涅槃の真因は唯信心をもってす。
(教行信証信巻)
浄土往生の因は、ただ一つ、信心である、ということです。
京都の中央で講義を受講する学生は、すでに地元で相当の学問を学んで来ていますので、この浄土真宗の基本に反する能化の講義に、誰もが疑問を持ちましたが、偉い先生の言うことなので、誰も反論せず、みんな黙っていました。
ところがただ1人、これは明らかにおかしいと感じた学生が、
智洞の講義録を持って地元の安芸(広島)へ帰っていったのです。
広島の僧侶が立ち上がる
智洞の講義録を手にした学生が、地元にたどり着いた時、
先生の大瀛は重い結核を患い、病床に伏していました。
しかし、浄土真宗の教えを正しく伝えるか、間違うかには、
後生の一大事が解決できるかどうかがかかっています。
永遠に浮かぶか沈むかという問題だけに、病床で本願寺の講義の話をすると、大瀛はカッと目を見開きます。
重い病をおして講義録を読むと、浄土真宗の危機が迫っていることを知ったのです。
しかし、学生の講義録ですから、何かの間違いかもしれません。
何かの間違いであって欲しいと思いつつ、大瀛は命がけで智洞の講義の不審をただす質問の手紙を書き上げると、本願寺へ送付したのです。
その質問は2つあります。
1つ目は、なぜ信心正因が間違いなのか。
2つ目は、なぜ三業帰命でなければならないのか、ということです。
ところが智洞は最高の立場にあり、地方の僧侶に自ら返事を出すまでもないと、部下に返答を書かせて送り返してきました。
しかし、今度は学生の講義録ではなく、本願寺の正式回答に違いはありません。
その返答に疑問を深めた大瀛は、さらに16の質問を送付しました。
これを「十六問尋書」といいます。
これには能化の智洞も返答できず、無視することにしました。
そして、1798年に開かれた蓮如上人300回忌法要で、智洞は法主に代わって話をし、その内容は、やはり心と口と体の三業でお願いしなければ救われないというものだったのです。
公式な場で三業帰命を主張したため、全国の僧侶や門徒に動揺が走りました。
こうして三業惑乱は、「三業帰命」か「信心正因」かという2つの派閥に分かれて、各地で激論が交わされるようになったのです。
広島の僧侶の出版
大瀛は何度も返答を催促しますが、智洞は答えません。
大瀛は、智洞の主張を論破する本を書くことにします。
結核を患っている大瀛は、何度も昏睡状態に陥りながら、命がけで執筆し、ついに書き上げることができました。
その名も『横超直道金剛錍』といいます。
しかし、原稿ができても、当時はパソコンもなければ、活字もありません。
出版するには、京都の仏教書の出版元に依頼する必要があります。
大瀛は病床にあるため、1800年春、2人の生徒が夜船でひそかに大阪へ行き、京都へ向かいます。
京都の6人の職人を雇い、1800年冬、ついに出版に成功したのです。
驚いた本願寺は、即刻発禁処分にします。
しかし、すでに700部が全国に送られた後でした。
それを読んだ全国の門徒は、智洞の誤りが完膚なきまでに打ち破られ、夢覚めた心地でした。
たちまち全国各地からたくさんの人が京都の本願寺へ詰めかけ、
法主の裁断を求めます。
ところが本願寺は、境内に牢屋を作り、回答を求めに来た者を投獄し、監禁しました。
こうして三業惑乱は、論争期を過ぎ、暴動期に入っていきます。
当時、京都では、
「極楽浄土の出店の寺に、なぜに地獄の牢がある」
という歌が流行ったといいます。
岐阜の門徒の決起
やがて1802年1月、美濃(岐阜)の大垣の門徒が河原に集まり、
ワラに火をかけてのろしをあげ、京都へ押しかけようとします。
一向一揆かと驚いてかけつけた大垣藩の役人たちに、岐阜の門徒たちはこう言います。
「智洞の三業帰命について、本願寺へ何回問い合わせても回答がありません。
ことは後生の一大事です。
この問題がハッキリしなければ、死ぬに死ねません。
この上は、みんなで京都へのぼり、命をかけて回答を求める覚悟です」
大垣の役人は、問題が大きくなると、幕府から責任を問われます。
必死に説得し、代わりに本願寺へ回答を要請することになります。
岐阜の門徒たちは一応状況を観察することにし、
大垣藩は本願寺へ回答を求めると共に、幕府へも事件の顛末を報告します。
幕府はそれまで、教義論争に介入しない方針でしたが、
一向一揆に似た不穏な空気を漂わせるこの問題は別でした。
寺社奉行の脇坂安董から「直ちに騒動をおさめよ」と本願寺に警告します。
本願寺内の争い
当時は、幕府に反旗を翻せば、忠臣蔵でもあったように、
大名でも即日切腹、領地没収となる時代です。
困った本願寺は、責任はすべて能化の智洞にあると幕府に返答したのです。
怒ったのは、智洞とその取り巻きでした。
1803年、智洞の信者1000人を集め、連日連夜、本願寺へデモを繰り返します。
その要求は2つありました。
1つは、教義についての責任と権限を智洞に戻すこと。
もう1つは、三業帰命を正しいと法主が認めること。
だんだんと暴力はエスカレートし、障子やふすまを蹴破り、
槍を突きつけて法主の奥座敷に乱入します。
法主は恐れおののき、ついに三業安心を正しいとする念書を書いたのでした。
この念書を宣伝し、智洞の派閥は、勢いを盛り返し、実権を握ります。
本願寺トップと地方の僧侶の対決
大瀛側も、正しい浄土真宗の教えを護るため、安芸(広島)からだんだんと京都の本願寺へ集まって来ました。
電車も車もない時代ですが、九州、中国四国、北陸などから
信心正因を主張する人々がぞくぞくと集まって来ます。
その数は1500人といわれます。
本願寺に騒動をしずめる力がなく、京都の役所である所司代に訴えます。
所司代によって、大瀛と智洞の討論がなされ、2人とも投獄されました。
本願寺に事態をおさめる力がないとみた幕府が介入し、
1804年、70数名の関係者が江戸へ送られます。
江戸の寺社奉行、脇坂安董は、大谷派(東本願寺)の香月院深励に学び、幕府の中で最も仏教に詳しいといわれていたのです。
大瀛は重い病におかされ、京都から35日間、かごに揺られて
江戸に着いた時は、もはや瀕死の重病人でした。
ところが、生死をさまよう重病人であった大瀛は堂々と論陣をはり、
寺社奉行も目を見張ります。
親鸞聖人が「涅槃の真因は唯信心をもってす」といわれた「唯」は、二つも三つもない、ただ一つである、なぜ三業帰命が必要なのかと「唯」の意味を問いただし、智洞を撃破したのでした。
その論争の後も、大瀛は寺社奉行に分かるように浄土真宗の他力信心を語り、口述筆記で安心書を作ります。
それを寺社奉行に提出した直後、大瀛は危篤に陥り、この世を去ったのでした。
その安心書を読んだ寺社奉行は、三業帰命は異安心であるという方針を固めます。
暴力事件に及んだ智洞には流刑の判決を下し、投獄します。
智洞は1805年、そこで獄死しました。
被告人が約70名あったので、判決が長引き、
すべて終了したのは、1806年7月11日でした。
本願寺自体も閉門百日となっています。
三業惑乱の争点
三業惑乱はどんなことが争点となっていたのでしょうか。
それは「たのむ一念」です。
たのむ一念について、蓮如上人の「領解文」には、こう教えられています。
もろもろの雑行・雑修・自力の心をふり捨てて、一心に「阿弥陀如来われらが今後の一大事の後生御たすけ候え」とたのみ申して候。
たのむ一念のとき、往生一定・御たすけ治定とぞんじ(蓮如上人)
「往生一定」とは、いつ死んでも極楽参り間違いなしとハッキリする、ということです。
助かったのやら助からんのやら、ハッキリしないのではありません。
「御たすけ治定」も同じ意味です。
言葉をかえて、繰り返し、いつ死んでも極楽参り間違いなしとハッキリする、と言われています。
それが決まるのが、たのむ一念の時なのです。
その時、雑行・雑修・自力の心がすたります。
雑行・雑修・自力の心がすたった時、往生一定とハッキリ助かります。
後生暗い心が破れます。
後生暗い心が明るくなります。
闇がなくなったらハッキリします。
「たのむ一念」が決勝点ですから、これほど大切なことはありません。
蓮如上人は「たのむ一念の所肝要なり」と教えられています。
「肝要」といえば、要の中の要です。
親鸞聖人の教えの中に、要は幾つかありますが、
要の中の要は一つしかありません。
これほど大事なところはありません。
要の中の要です。
その親鸞聖人の教えで最も重要な、「たのむ一念」について、
智洞と大瀛が激突したのです。
どのように激突したかというと、分かりやすく言えば、
能化である智洞は、「心と口と体でお願いしなければ助からない」という三業安心です。
「たのむ」というのは、阿弥陀仏に心でお願いし、口でお願いしますと言い、体でお願いすることだ、と教えたのです。
それに対して大瀛は、お願いしなければ助からないというのは自力だ、蓮如上人は、雑行・雑修・自力の心をふり捨てよ、と教えられている。
心と口と体でお願いしなければ助からないというのは自力だから、これをふり捨てた時に助かる。
このように、三業帰命を正したのでした。
たのむ一念までは自力で、
たのむ一念に自力がすたり、他力に入ります。
自力と他力の変わり目が、たのむ一念です。
ここで助かるか助からないか決まる、地獄と極楽の分かれ道です。
ここを間違ったら永遠に浮かばれません。
その最も重要な「たのむ一念」について、
智洞と大瀛の180度真逆の主張が正面衝突し、
大瀛が智洞の誤りを粉砕したのでした。
三業惑乱の現代への影響
やがて閉門が解け、開門した本願寺は、法主の本如の名で、
『御裁断の御書』を発表します。
この「三業帰命」と「信心正因」の対決した10年にわたる三業惑乱によって、「三業帰命」は退けられましたが、振り子がふれるように、今度は帰命の一念にふれることを恐れるようになり、浄土真宗の肝要である「たのむ一念」にふれなくなってしまったのです。
そして、智洞の側の書籍も絶版にすると同時に、『横超直道金剛錍』も絶版にします。
こうして、「三業帰命」を正した勢いで、振り子が逆側にふれるように、
また「十劫安心」に逆戻りしてしまい、現代にいたるのです。
このように、
「十劫安心は間違いだ」と叩けば、三業安心にふれます。
「三業安心は間違いだ」と叩けば、十劫安心にふれます。
他力信心は、十劫安心でも三業安心でもないのですが、
振り子は中央に止まりません。
現代の浄土真宗では、
阿弥陀仏の救いは自覚できる人もいるが、自覚できない人もいる、
私たちはすでに救われているのだから、聞き歩いたり求めたりしなくても、誰でも死んだら極楽に往ける、
と思われている状態です。
それは十劫安心という異安心です。
本当の親鸞聖人の教えは信心正因です。
ハッキリと他力信心を獲得しなければ救われません。
では、真実の他力信心とはどんなものなのか、
その本質を小冊子とメール講座にまとめておきましたので、
今すぐ以下からご覧ください。
浄土真宗の本質を学ぶ
浄土真宗の教えの本質、苦しみの根元をメール講座にまとめました。
詳しくは以下のページで確認してください。
関連記事
著者紹介
この記事を書いた人

長南瑞生
日本仏教学院 学院長
東京大学教養学部にて量子統計力学を学び、卒業後、学士入学して東大文学部インド哲学科で学ぶ。
仏教を学ぶほど、その深い教えと、それがあまりに知られていないことに驚く。仏教に関心のある人に何とか本物の仏教を知ってもらおうと10年ほど失敗ばかり。たまたまインターネットの技術を導入し、日本仏教アソシエーション、日本仏教学院を設立。著書2冊。通信講座受講者4千人。メルマガ読者5万人。執筆や講演を通して一人でも多くの人に本物の仏教を知ってもらえるよう奮戦中。
仏教界では先駆的にインターネットに進出。メールマガジンや、X(ツイッター)(@M_Osanami)、ユーチューブ(長南瑞生公式チャンネル)、インスタグラム(日本仏教学院公式インスタグラム)で情報発信中。先端技術を駆使して伝統的な本物の仏教を一人でも多くの人に分かりやすく理解できる環境を作り出そうとしている。メールマガジンはこちらから講読が可能。